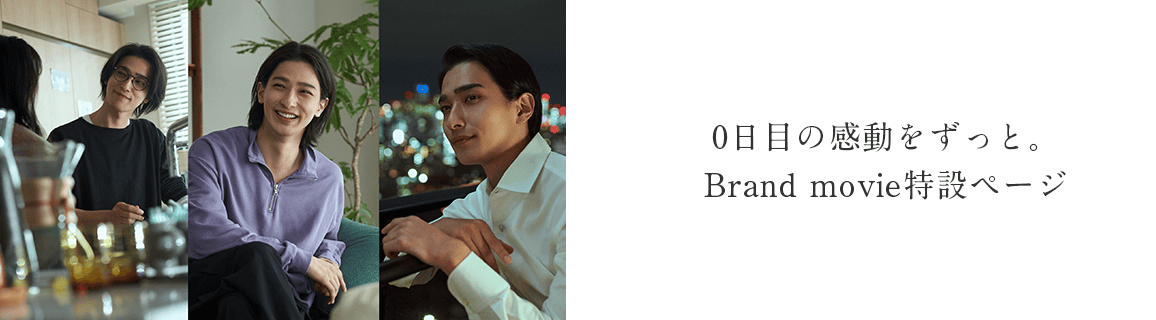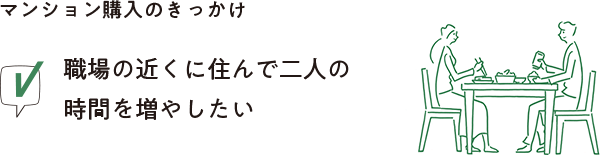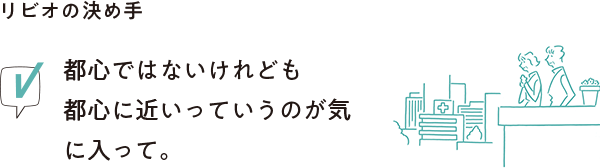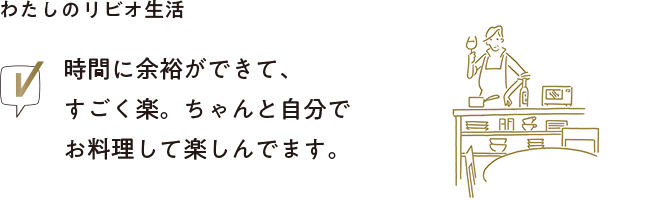美食とアートが融合した特別な夜。スペシャリストが語る「現代アートの楽しみ方」イベントをレポート

2025年6月9日、LIVIO主催の特別イベント「参加型!現代アートの楽しみ方入門ガイド」を六本木のギャラリー「アートかビーフンか白厨」にて開催しました!
myLIVIO会員のみなさま限定で実施されたこのイベントは、美味しい台湾料理を味わいながら、現代アートの奥深い魅力に触れる贅沢な時間となりました。

イベントの講師には、現代アートのスペシャリストである塚田萌菜美さんをお迎えし、普段は難解に感じられがちな現代アートを、歴史的背景から丁寧に解説していただきました。参加者のみなさまは、料理とドリンクを楽しみながら、リラックスした雰囲気の中でアートの世界に深く浸ることができました。
開催当日の様子を、現地からの写真と共にレポートします!
そもそも「アート」はどんな意味?専門家が案内する、知的好奇心を刺激する特別講座

塚田萌菜美さんは、成城大学文芸学部芸術学科卒業後、同大学院で美学・美術史を専攻された、現代アート界の第一線で活躍するプロフェッショナルです。オークション会社での富裕層向けアート売買営業やアドバイザリー業務を経て、現在は株式会社The Chain Museumにて企業向けキュレーションやコレクション形成コンサルティングを担当されています。
「今日は完全にカジュアルな形で進めていこうと思います。皆さんお食事や飲み物を楽しみながら、最初は少しアカデミックなお話もできればと思います」と塚田さんが挨拶すると、会場には温かで知的な雰囲気が広がりました。

講座は「アート」という言葉の定義から始まりました。塚田さんは「『現代アートがわからない』とよく言われるのですが、そもそもみなさんが言う『アート』が本当に同じことを指しているのか、まずは目線合わせをしなければなりません」と切り出します。
英語の「art」が明治時代に日本へ入ってきた際、その意味を完全に理解しないまま「芸術」や「技術」と訳されたことを踏まえ、実際に英語の「art」は芸術、技術、人工的なものといったすべてを含む広い概念であることを説明。
その点では、日本語の「芸術」は英語の「art」の一部しかカバーしていないため、欧米の人々との会話では認識のずれが生じる可能性がある、という興味深い指摘に、参加者の方々も「なるほど」といった表情を浮かべていました。
また、現代アート(コンテンポラリーアート)については、「同時代に生きている人の作品」という意味で、一般的には1945年以降、第二次世界大戦後の作品を指すと解説されました。
カメラの発明が起こした芸術革命!400年間の変化を読み解く
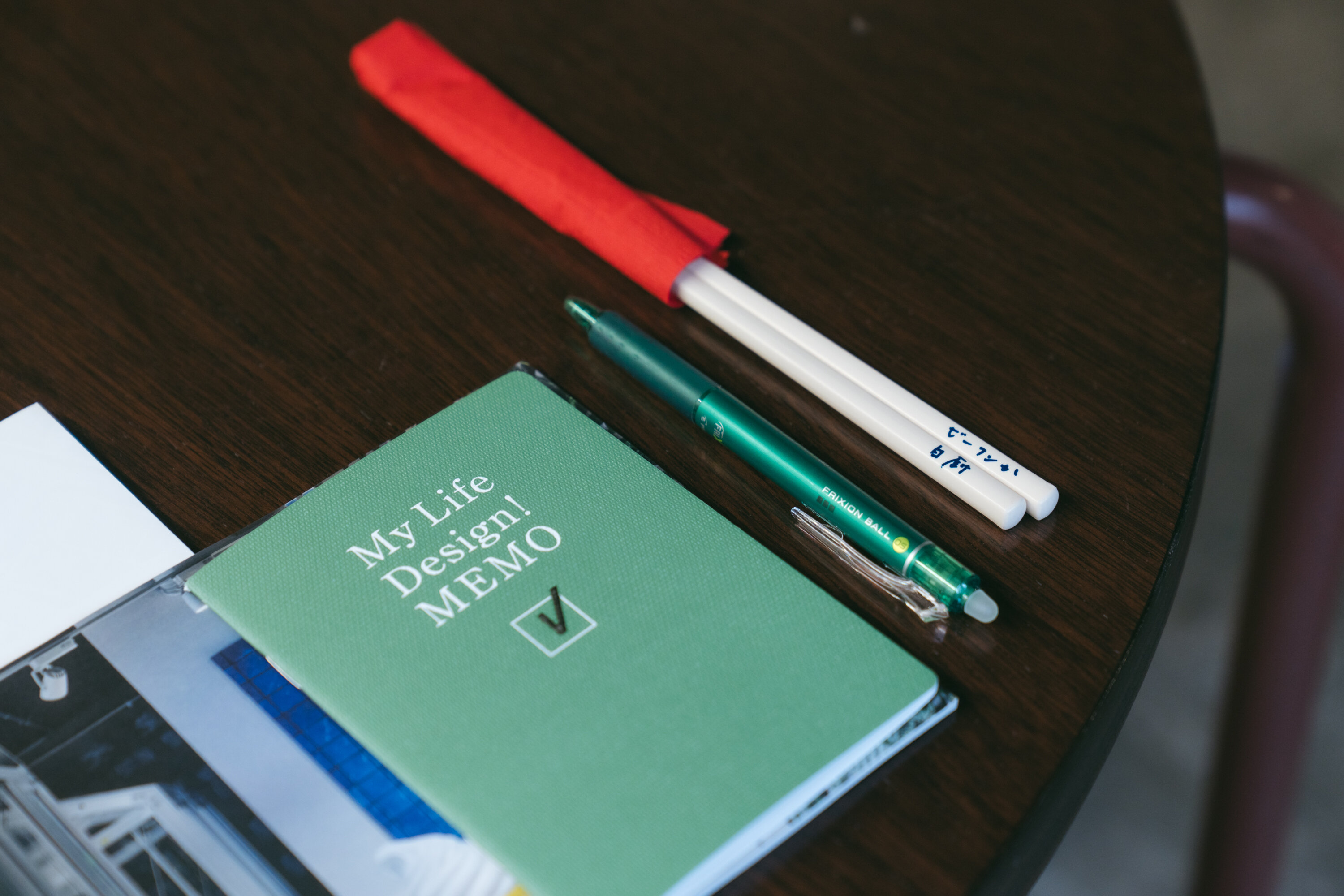
塚田さんは、レオナルド・ダ・ヴィンチの「モナリザ」(1503-19年頃)とマルセル・デュシャンの「泉」(1917年)を比較し、400年の間にアートの見方がどのように変化したかを解説しました。
特に印象的だったのは、1800年代から1900年代の100年間に焦点を当てた解説です。1800年代前半は肖像画などが主流で、現実を美化する傾向がありました。しかし、この時代の大きな転換点としてカメラの発明を挙げ、「今まで美化して描いていたけれども、そのままを写すならカメラがある。アーティストたちは『カメラにはできないことをしよう』と模索し始めた」と説明。
カメラの発明により、印象派の誕生につながったという流れは、参加者にとって新鮮な発見だったようです。印象派の画家たちが屋外に出て、光の印象を捉える手法を確立し、色の分割などの技法も生み出したという解説に、参加者がメモを取る姿も見られました。
現代アートは「推理ゲーム」に?デュシャンが変えた芸術の見方

印象派以降、フォーヴィスム(色彩の解放)、キュビスム(形の崩壊)など、様々な表現実験が行われていきます。そして1917年、マルセル・デュシャンが「泉」という作品で、既製品の男性用便器にサインを書き入れるだけで「作品」としたことに端を発し、「レディメイド」という手法を生み出しました。
この出来事により、アートの見方が大きく変化したと塚田さんは指摘します。「目に見えているものだけではわからないので、(鑑賞者が)まずは思考しなければいけない」という新しい鑑賞方法が生まれたのです。
塚田さんは現代アートの鑑賞を「推理ゲーム」に例えて説明しました。デュシャンが行ったことは「事件が起こった現場」を作品にしたようなもので、見る人はそこから「足跡」や「指紋」を見つけ出し、「連想ゲーム」を通じて作品の意味を読み解いていくのだと解説。この比喩に、参加者の方々も現代アートへの理解を深めていかれる様子でした。
その後も現代アートは、ポップアート、コンセプチュアルアートといった激動の1960年代を経て、地球規模やストリートにも染み出していく1970〜1980年代、そして主題を「社会と個人」に求める1990年代と変遷を続けながら、今日にまで至っているのです。
グローバル化で変わるアート界。多様性が生み出す新しい価値

講座の後半では、現代アート市場の変化についても触れられました。2016年から2020年にかけて、アメリカ中心だった市場に中国のシェアが拡大してきたことで、「今までのアメリカ中心で進んできたアートの考え方に、中国やアジア系の人たち、それ以外の人たちの話が加わり始める」という変化が起きたと説明。
特にコロナ禍で社会機能が停止した際には、「今まで除外されてきた人たちはどういう人がいるのか、むしろなぜ今まで一部の人しかいなかったのだろう」という問いかけが起こり、歴史の解体と再構築が始まったと指摘。
女性アーティストやジェンダー・クィアの作家たちの再評価、ストリートアートの認知、日本のアニメ・漫画文化の影響なども紹介され、現代アート界の多様性について深く学ぶことができました。
実際の作品を前に体験する「対話型鑑賞」

講義後には、会場に展示された実際の作品を前に「対話型鑑賞」を実践。塚田さんは参加者に「何が見えるか」「違和感はないか」と問いかけ、鑑賞対象となった作品の中の「目」と「他の部分」との違いに注目するよう促しました。
作品の中のしましま模様は「ダズル迷彩」と呼ばれる海軍が使用する迷彩パターンであることや、目の中にはスマートフォンの画面が映り込んでいることを解説。この作家が「人間とテクノロジーのあり方、それをどう見せたい/どう見られたいかをカモフラージュして表現している」ことを説明しました。
「現代アートは一つの解釈に集約する必要はありません。連想ゲーム的に広げていけばいいのです」と塚田さんが強調すると、参加者の方々も安心したような表情を見せ、各自の背景や経験によって見え方が違うからこそ、周りの人と対話することの価値を実感されているようでした。
AIの時代だからこそ重要な「じっくり見る」体験

イベントの締めくくりとして、塚田さんは現代におけるアート鑑賞の意義について言及しました。「AIがどんどん出てきて、様々な仕事がなくなってきています。本を読まなくても要約で大筋をつかんでしまうことができる時代において、物をじっくり見る機会はなくなっていませんか」という問いかけは、参加者の心に深く響いたようです。
「思考を誰かに委ねてしまうと、実は目の前の人もほとんどよく見ていないということに陥ってしまう」という危険性を指摘し、現代アートを見慣れて体験することで、目の前にある事象に潜む意味に気づける訓練ができる、と説きました。
特別な空間で味わう、アートと美食の融合

今回のイベント会場となった「アートかビーフンか白厨」は、塚田さんが所属する株式会社The Chain Museumがプロデュースするギャラリーです。現代アート作品が展示される空間で、台湾料理をベースとした美味しい料理を味わいながらの贅沢な時間は、参加者のみなさまにとって特別な体験となりました。
前菜の盛り合わせや名物のビーフンを楽しみながら、知的好奇心を刺激する講座に参加する。このイベントを通じて、普段は難解に感じられがちな現代アートを、歴史的な文脈から理解し、自分なりの解釈で楽しむ手がかりを得られた参加者のみなさま。感性を豊かにする特別な夜を過ごされた表情がとても印象的でした。
LIVIOでは今後も、このような知的好奇心を刺激し、豊かな住まいと暮らしのヒントを提供するイベントを開催してまいります。次回のイベントもぜひお楽しみに!
開催済イベントの概要
イベント名: 参加型!現代アートの楽しみ方入門ガイド
開催日時: 2025年5月17日(土)
開催会場: アートかビーフンか白厨(六本木)
講師: 塚田萌菜美さん(アートスペシャリスト / 株式会社The Chain Museum)
対象: myLIVIO会員限定